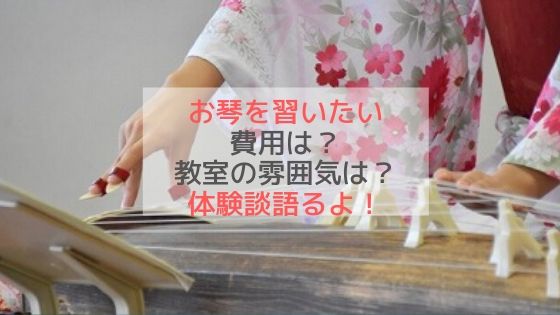
こんにちは!
ようこそ。ぽんこくらぶへ!
お琴を知っていますか?
日本で古来からある楽器として有名ですよね。
実は6歳から18歳になるまでお琴を習っていました。
現在は習っていませんが、自宅で孤独と戦いつつ一人レッスンに励んでます。(月一ですが。笑)
今回は、お琴をはじめてから33年!お琴の経験者が語るお琴の費用や教室のこと、個人的な体験談を含めて他では聞けない秘密の情報満載でお届けしたいとおもいます。
お琴は外国人ウケも抜群です!
子供の習い事や、花嫁修業にも。
女性が多いけど男性にも習ってほしい。
あなたもお琴習ってみない?
お琴を習ったきっかけ
お琴楽しいですよ。
お琴を教室に行って習ったのは実質12年です。
小学校1年生から高校3年生の頃までお琴を習っていました。
お琴には生田流と山田流という流派があります。
私は山田流のお琴教室に習いに行っていました。
主に久本玄智先生の曲を弾いていました。
久本玄智(ひさもと げんち、1903年(明治36年)4月-1976年(昭和51年)3月21日)は、島根県生まれの作曲家、ピアノ演奏家、邦楽演奏家である。
5歳で失明した。東京盲学校卒業。山田流筝曲を初代萩岡松韻(しょういん)に、ピアノ、声楽を舟橋栄吉に学ぶ。東京盲学校の教諭として勤務。東京教育大学教授を務めた。
日本で初めて点字楽譜で演奏した。東京盲学校出身の山田流筝曲家山川園松(1909-1984)、初世宮下秀冽(1909-1993)などと若い世代の新作邦楽は新邦楽と呼ばれた。
昭和51年(1976年)3月21日死去。享年72。
引用 Wikipedia 「久本玄智」より
久本玄智先生は5歳で全盲となってしまいましたが、数々のお琴の名曲を生み出した方。
お琴の音色を聴かせる生田流とは違い、
久本玄智先生の曲は華やかでアップテンポなんです。
とにかく私は好きなんです。久本玄智先生の曲。
弾いていて楽しい気分にさせてくれる!
そんな曲がとても多いのです。
習ったきっかけは、6歳の頃、テレビでお琴を見て「これがやりたい!」この一言でお琴を習うことになりました。
ちょうど父の職場の方がお琴の先生をしていて、すぐに教室に行くことに。
まだ小さかったので習いたての頃のことは残念ながら全く記憶にありません。
ただ小学生高学年の頃には、
いつの間にかす~らすら弾けるようになっていて
ありがたいことに先生の一番弟子くらいのレベルに!(と勝手におもってます。笑)
先生がとても優しい心の広い方で褒め上手。
下手でも「上手上手!」といつも褒めてくださる先生でした。
褒められると下手でも上手な気がしてきますよね。
だから楽しく長~く続けることができたんですね。
残念ながら先生はお亡くなりになってしまったのだけれど、もし先生がご存命だったらまだ習いにいっていたかもしれません。
お琴を習う費用は?安くはないけど手が出る金額

私が習っていたお琴の教室は、
東北地方の某教室でした。
お弟子さんは15人くらい。
ほとんどが年配の女性。
先生の職場の同僚の方が多かったですね。
私は一番若手でした。
その後少しずつ私よりも若い子が入ってきました。
やはり小学生の低学年で始めてましたね。
今から30年ぐらい前の話で申し訳ないのですが、お琴教室のお月謝は2千円でした。
お琴を習って2千円は驚きの安さですよね。
その後、お琴を習っていたお弟子さんたちが富裕層で、「月謝が安く先生に申し訳ない」ということで千円の値上がり。
お琴教室の月謝は3千円になりました。
ウチは富裕層ではなかったので千円の値上がりは正直きつかったとおもいます。笑
ちなみにお琴を習うと楽譜も購入する必要があります。
先生が事前に購入してくれているので先生に楽譜の代金をお渡しします。
新しい曲を学ぶたびに楽譜代がかかります。
楽譜の金額としては300円から700円くらいでした。
童謡はかなり厚みのある楽譜で1400円でした。
ただ30年前の楽譜の値段なので…、今はもうすこし高いかもしれませんね。
お琴は先生の教室に用意されているのを使えます。
習ってから当面の間は買いませんでした。
結局お弟子さんたちはほとんど自分用のお琴をもっていたので、うちも買うことに。
お琴はすべてセットで購入しました。
お琴にはいろいろと必要なお道具類があります。
ご紹介すると下記のとおり。
・お琴用の爪
・調子笛(琴の調子を合わせる笛)
・楽譜を置く譜面台(木製)
・折り畳み式譜面台(スチール製)
・琴柱(糸を立てる柱)
・琴台(琴を支える台)
・立奏台(椅子に座って弾く時用の琴を支えるための台)
・お琴全体を覆うための布製カバー
・持ち運びに便利な厚手の収納カバー
・楽譜入れ
・琴爪入れ(ケース)
・琴柱入れ(専用ケース)
一式すべて合わせた金額は価格25万円くらいだそうです。
(母情報。30年前の価格です。)
ちなみに和楽器専門の和楽器市場でも購入することができます。
お値段など参考にしてみてくださいね。
楽譜入れや琴爪入れはおそろいの柄で統一。
琴柱入れも同じような色合いのもので合わせました。
ケースなどすべて和柄で、すごくきれいなんです。
選んで購入した時はとてもワクワクしたのを覚えています。
ちなみにお琴のセットはアマゾンでも5万円くらいで買えます。
山田流と生田流それぞれのお琴がセット価格で売っています。
【山田流のお琴セット】
【生田流のお琴セット】
お琴自体の質としてはどうなのか…?
いささか不明ですね。
現代ではネット通販もありですが、もしお琴を購入するなら先生が取引している信頼する業者さんに頼むのが一番です。
高くても本当に良いお琴に出会えます。
買えば一生もの。
私は宝石もなにも持っていないけど、
お琴は今でも自分の唯一無二の宝です。
そんな大切な私のお琴ですが、最近夫に邪魔もの扱いされていて不憫です。
お琴大事にしなきゃね。
買ってくれた私の両親には感謝しかありません。
お琴自体は高いけど、立派なピアノやバイオリンに比べると安いかもしれませんね。
お琴を習って大変だったことを挙げてみる

なにが大変って。
お琴ってものすごく大きいんですよ。
全長182㎝だそうです。
大柄な男の人の身長と同じくらいですよね。
お琴の発表会は夏と冬の年に2回ありました。
そのとてつもなく大きいお琴を発表会のたびに、車に入れて運ばなくてはいけません。
本格的に習うのであれば自家用車は必須かもしれませんね。
タクシーでもお琴を運べなくはなさそうですがどうでしょう?
断られる可能性もなきにしもあらず…?
お琴を車に入れるときがものすごく大変で。
トランクを開けて後ろから車の前方に向けて突っ込みます。
お琴がねまた重いんですよ。
母と二人がかりでヒーハー言いながらお琴を車に押し込んだのを思い出します。
そして発表会のときの持ち物はお琴だけじゃなくて、先ほどご紹介した色々なお道具があるんです。
さきほどご紹介したセットで購入した譜面台、琴台、楽譜、琴柱、ケース類など。
これら全てを持参する必要があります!!
お琴を運ぶことも大変ですが、
何よりも大変なのが、お着物!!
お着物を着付けて、髪もセットして発表会に行く必要がありました。
夏の発表会は浴衣でOKでした。
浴衣は1万円もあればかなりいいものが買えますよね。
最近だとユニクロでもオシャレな浴衣が安いので買いやすいですよね。
ちなみに普段のお琴教室での練習は普段着でOKです。
そして発表会のたびに毎度同じお着物を…というわけにもいかないので、それなりに何着も用意せざるを得ません。
着物は少しずつ増やしていって、成長するごとに仕立て直したり。
3から5着くらいをローテーションで着ていました。
もちろんただの一般家庭なのでお高い着物は着ていません。
ただ高見えするような着物を買ってもらっていました。
私はピンク色の小花柄や蝶々の柄の着物が好きでよく着ていました。
母に確認したところ1枚10万円以下くらいで買っていたそうです。
1枚5万円だとしても3枚買って15万円!
結構な値段ですよね。
本当にありがたいです。
最近は、リサイクルで着物を売っているので利用してみると安く済みますよね。
昔は着物のリサイクルショップがなかったから普通に買うしかありませんでした。
私の祖母は着物の着付けができる人。
発表会の日は祖母に着付けをしてもらっていました。
髪の毛は飾りを適当につけて、ハイおしまい!
そんな感じで発表会の準備は乗り切っていました。
1~2回、大きい発表会のときに美容院で着付けと髪のセットに行きましたが、着付けは締め付けがひどく体調が悪くなるほどでした。
やはり祖母の着付けが一番でしたね。
髪の毛のセットもスプレーでバリバリになるほど固められて臭いもキツかったです。
発表会は、地方の文化会館を貸し切りにして行います。
ほとんど家族など関係者しかいないので気が楽でした。
お弟子さんの人数の多い教室ではなかったので、
発表会ではたくさん弾かせてもらっていました。
準備は大変でしたが、発表会自体はとても楽しかったです。
小さい頃から舞台に立つ機会が多いと自然と慣れます。
本当はものすごく引っ込み思案な子供でしたが、ごくあたりまえに舞台に立っていました。
発表会が終わると料亭などの一室を貸し切りにして打ち上げをします。
会費は5千円くらいでした。
私の母もいつも参加!
母がいつも同伴でいてくれたのでとても心強かったですね。
お琴教室は大人しかいない場だったので、子供一人だと心細いですよね。
もしお子さんがお琴を習いたい!というときには発表会だけではなく、そういったお付き合いもあることを頭に入れておいたほうがいいかもしれません。
関係者しかいない通常の夏と冬の発表会では、とくに大変ではありませんでした。
でも一般のお客さんを入れるパターンの発表会ではチケットを5枚くらい買わされ、知り合いに売らないといけないということもありましたね。
そんなに高額なチケットではありませんでしたが、多少負担ですよね。
結局ウチでチケット代を負担して知り合いの方にチケットを差し上げていました。
他に大変だったことといえば、普段は椅子に座ってお琴を台に載せて弾くので楽ですが、たまに正座で弾くこともあります。
慣れると1時間くらいは正座をしても辛くないのですが、慣れるまでが大変でした。
・お琴の発表会でお琴と道具を運ぶのが大変!
・お琴の発表会で着物の着付けとヘアセットが大変!
・お琴の発表会用に着物を買うのが大変!
・お琴の発表会のあと打ち上げの出席が大変!
・出演する舞台のチケットを買わされて知り合いに売るのが大変!
・お琴を長時間正座で弾くのが大変!
お琴教室の雰囲気は?

私が通っていたお琴教室では、先生と一対一で教わっていました。
お琴を習っている人あるあるなのですが、その教室以外のこと何も知りません。笑
なので私自身が通っていた教室のことしか知らないのです。
当ブログは山田流の久本玄智先生の曲を主に弾く教室の情報になります。
生田流の教室と比較したい人とかいたら…ごめんねっ!
そんな私が通うお琴教室は、普段他のお弟子さんとはあまり会いません。
お琴を弾くにはまず調子を合わせるところから始まります。
この調子を合わせるというのが一苦労。
慣れると耳でなんとなく覚えられました。
調子を合わせるための笛があるので普段はそれを使います。
調子が合ったら、まず先生の見本を聴きます。
そのあと先生と一緒に弾くというように教わりました。
先生が海のごとく山のごとくやさしかったので、
毎度出来が悪くても常に褒められていました。
たぶん調子に乗って自分はお琴がうまいんだ!と勘違いしつつ…、
ちょっとずつ上達していったんだとおもいます。
一時は芸術系の超有名大学のお琴学科を受験しようとしたぐらい勘違いしていましたね。
ほんとにやめてよかったです。
身の程知らずにもほどがある。
ちなみに母は褒めるどころかけなすような人でした。
けなされる人の脇でお琴を弾くのってちょっと辛いですよね。
というわけでお琴をあまり家で練習しませんでした。
もっと家で練習していたら…、
母が褒め上手なら…、
もっと上達していただろうに、超有名芸術大学出だったかも?と悔やみます。
でもお琴を弾くまでのセッティング自体がものすごく手間なんですよね。
自宅で練習しなかったことを母のせいにしてますが、結局モノグサな性格だからあまり家で練習しなかったんですよね。
ごめんよ。母さん!笑
さてお琴教室ですが、私の通っていた教室ではお琴の先生の旦那さんが尺八の先生だったんです。
ということで発表会間際になると尺八のお弟子さんとお琴のお弟子さんが勢ぞろいして先生の一室に集まり一斉に練習をします。
総勢30名以上はいたとおもいます。
部屋はすし詰め状態。
熱気がすごい。
先生の家は隣近所からクレームが来なかったのかな。笑
発表会前には2時間くらいかけて延々と練習します。
結構ハードですよね。
練習のときはお琴はほぼ正座。
正座が段々と辛くなるんですよね。
でも尺八と合わさって合奏するととても素晴らしいんです。
曲が完璧に仕上がるんですよね。
だから練習も辛くはなかったです。
(でも正座は辛い。)
最高に楽しかったです。
お琴教室を選ぶなら、旦那さんが尺八の先生をしているお琴の教室が最高におすすめですよ。
なかなかレアかもしれませんが。
田舎だとご夫婦でお琴と尺八をする先生は一定数いましたよ。
探してみてくださいね。
さいごに
唐突にはじまったお琴のブログ。
今回はこのへんで。
ちまたでお琴を習っている人は珍しいので、
お琴を弾けるだけで「すごい人」認定されることがあります。
全くそんなことはありませんが、そんな勘違いをされるのも悪くはないものです。
お琴を弾けると間違いなく外国の人には驚かれます。
いつか家で民泊をして、泊めた外国人の方にお琴を聴かせたいと考えています。
あと30年くらい先のことなので、そのころにはもう少し人様に聴かせられるような腕前になっているといいのですが。
それではまた!
最後までお読みいただきましてありがとうございました!!



